


Fleeting
泡沫
H15×W80×D150mm

A World I Do Not Wish For
望まない世界
H20×W150×D160mm

The Last Thing I Saw
最後にみたもの
H50×W145×D230mm

John Langdon Down
ジョン・ラングドン・ダウン
H30×W100×D200mm

Silent Illumination
寂光
H30×W160×D195mm

Give Me Everything
ぜんぶよこせ
H25×W120×D175mm

No Changes
変化はいらない
H40×W170×D205mm

Hope in a Deadlock
手詰まりの希望
H50×W140×D180mm

Parade
聖者の行進
H65×W90×D90mm

Demons Out, Fortune Out as Well
鬼も外、福も外
H70×W140×D140mm

People Who Start, People Who Can’t Finish
はじめるも人、おえられぬも人
H120×W80×D35mm

Fake, Fake
借着よ借着
H300×W150×D200mm

Nature, Mastery, Imitation, or Sacrifice?
自然か主か真似事か供犠か
H80×W70×D70mm

Special Attack
桜花
H220×W60×D60mm

Dream Night
夢寐
H140×W55×D55mm

Beautiful World
美しき世界
H225×W185×D185mm

Surrounded by Silence
静寂に包まれて
H220×W130×D130mm

Someday
またいつか
H285×W130×D130mm
Lenticular
This work presents a disposable mouse wrapped in a container.
In Japan, both mice and containers are essential to daily life.
Yet once used, they are easily discarded—this is the current reality.
To prompt a shift in this mindset, the concept of lenticularity—in which perception changes depending on the viewer’s angle—was adopted.
Each work’s title also incorporates words that echo themes of “parting” and “preciousness,” inspired by The Tale of Genji and its passage:
“To part, for it is the limit.”
The following is a poem composed by connecting those titles:
“What did John Langdon Down see in the end—serene light or fleeting foam?
Hope at a dead end, the saint marches on.
No need for change, give me everything.
Demons out, blessings out.
It is humans who begin, and humans who fail to end.
Dreaming beneath cherry blossoms—
so wear a borrowed robe, a borrowed robe.
Let’s meet again someday.
In an unwanted world, in a beautiful world,
where even nature, the master, the imitation, and the sacrifice
are all wrapped in silence.”
And one day, I too will be discarded.
What will I part from, and what will wrap around me?
レンチキュラー
本作は、使い捨てにされたマウスを容器で包んだ作品である
日本においてマウスと容器は、人の生活を支える存在でありながら、一度使用されると容易に捨てられてしまう現状がある
この状況に変化を促すため、視点によって見え方が変わる「レンチキュラー」の概念をコンセプトとし、各作品のタイトルには、源氏物語「限りとて別るる道」に通じる「別れ」や「尊さ」の言葉も包みこむように添えた
以下は、それらのタイトルをつなげた詩である
「ジョン・ラングドン・ダウンが、最後に見たものは寂光か、泡沫か。手詰まりの希望、聖者は行進をする。変化はいらない、ぜんぶよこせ。鬼も外、福も外。はじめるも人、おえられぬも人。桜花に夢寐、それに借着よ借着。またいつか会いましょう。望まない世界で、美しい世界で、静寂に包まれた自然も主も真似事も供犠も」
やがて私も使い捨てられ、何と別れ、何に包まれるのか
Category: Sculpture, Photography
Medium: Mixed Media
Dimensions listed individually
Photo Dimensions: H594×W841×D30mm
Photography: Yudai Nakaya
Collection: Private Collection
Year: 2024
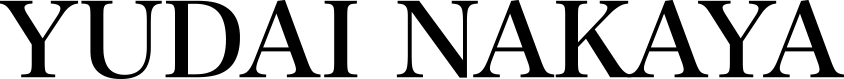
グランプリ受賞作品作品解説 & インタビュー
限りとて——捨てられ、包まれ、眼差されるもの
容器とマウス、日常に溶け込み、やがて静かに捨てられていくものたちが、中谷の手により、美術作品として異なる光を帯び始める。グランプリを受賞した本作「レンチキュラー」シリーズは、使い捨てられた実験用マウスを容器で包み込んだ立体作品である。だがその行為は単なる造形ではなく、社会における消費と廃棄、そして命の扱われ方への根源的な問いかけとして提示されている
制作の動機には、作家が数年前に訪れたカンボジアでの体験が深く関わっている。観光ガイドには載らない、更生施設や労働現場を訪れた際、衛生とは程遠い容器に盛られた食事と、それを口にする人々の姿に衝撃を受けた。清潔な生活に囲まれている自分と、容器ひとつをめぐる衛生観・価値観の差。その記憶が、使い捨てられる容器と命への視点を変えたのだという
容器は、私たちの便利な暮らしを象徴する存在だ。日本国内のプラスチック廃棄量は年間約823万トン(2022年)。その87%がリサイクルされているとされるが、地球規模では毎年800万トンが海に流出し、2050年には海中のプラスチックが魚の重量を超えるという予測もある。便利さの裏にある、見えにくい代償。それを私たちはどこまで自覚しているだろうか
一方の「マウス」は、年間300万匹(2019年)近くが日本国内の実験で使用される。その多くが、使命を終えると破棄される。インタビューで作家は、大学関係者の言葉をこう伝えている。「捨てることに抵抗はない。ただし、実験によって生活がよくなる、その誇りもある」と。効率と目的のために見過ごされがちな命が、実験という名のもとに消費されていく構図。その現実を、アートの場にそっと差し出している
シリーズ名に冠された「レンチキュラー」は、見る角度によって像が変化する印刷技術を指す。中谷はこの仕組みに、視点の多様性や認識の曖昧さを重ね合わせた。どのような立場から見るかによって、命の価値も、廃棄されるものの意味も変わってくる。「何が存在し、どう認識するか」。作家の問いは哲学的でありながら、否応なく、私たちにとって現実的なものとして突きつけられる
さらに、作品タイトルの一部には「源氏物語」の一節「限りとて別るる道」に由来する語彙が含まれる。それは、別れの悲しみと命の尊さを内包しつつ、鑑賞者の心に静かに忍び寄る詩のような仕掛けだ。中谷は語る。「美しい世界で、望まない世界で、何と別れ、何に包まれていくのか」。使い捨てられるマウスの姿に、自身の存在すら重ねるその眼差しは、作品を単なる批評や告発にとどめず、詩的な哀切を帯びさせている
見る者の視点を揺さぶる「レンチキュラー」は、今この社会に対して、沈黙の中に強い疑問を突きつけている。いま、あなたが見ているものは何か。その視線そのものが、すでに作品の一部なのかもしれない
本作は「何が存在するのか」「それをどのように知るのか」という、視点の多様性と認識の根源的な問いから生まれる、存在論的であり、同時に認識論的な試みと言えるだろう
Art Commentator: Haku Kato